イーサリアム Interop ロードマップ:大規模採用の「ラストワンマイル」をどのように解決するか
クロスチェーンから「インターオペラビリティ」へ、Ethereumの多くの基盤インフラが、大規模な採用に向けてシステム統合を加速させている。
著者:imToken
Web3の世界では、「クロスチェーン」からインターオペラビリティ(Interop)まで、常に語られてきた長寿なストーリーです。
もちろん、多くの人が両者の意味を厳密に区別していないかもしれませんが、一言でまとめると、クロスチェーンは資産に焦点を当て、「移動」の問題を主に解決します。一方、インターオペラビリティ(Interop)は資産、状態、サービスなど複数の次元をカバーし、「協働」の問題を解決することを目指しています。
実際、モジュラー型のストーリーがL1/L2の数と異種性を押し上げるにつれ、ユーザーと流動性がさらに分散され、インターオペラビリティはクロスチェーンよりも理想的な最終形態として広く認識されるようになりました——ユーザーはどのチェーンにいるかを意識せず、一度だけ意図を提出し、システムが最適な実行環境で自動的に操作を完了します。
そして最近、EF(Ethereum Foundation)が新たなUXロードマップを発表し、出金遅延、メッセージ伝達、リアルタイム証明に関する一連のエンジニアリングの進展とともに、インターオペラビリティのパズルが着実に組み合わされつつあります。
一、「Interop」とは何か?
簡単に言えば、「インターオペラビリティ」は単なる「資産ブリッジ」以上のものであり、システムレベルの能力の組み合わせです。
それは異なるチェーン間で状態や証明を共有でき、スマートコントラクト同士がロジックを呼び出し合い、ユーザー側が統一されたインタラクション体験を得られ、各実行環境がセキュリティ境界で同等の信頼性を維持できることを意味します。
これらの能力が同時に満たされたとき、ユーザーは本当に価値活動そのものに集中でき、ネットワークの切り替えや重複認証、流動性の断片化に悩まされることがなくなります。これはクロスチェーンエンジニアリングの終局とも呼応しています:ユーザーが価値の流れそのものに集中できるようにし、チェーン間の障壁を意識させない(参考記事『クロスチェーンエンジニアリング進化論:「アグリゲートブリッジ」から「アトミックインターオペラビリティ」へ、私たちはどんな未来に向かっているのか?』)。
特に2024年以降、モジュラー型のストーリーが全面的に爆発し、ますます多く、より細分化されたL1やL2が登場することで、インターオペラビリティはもはやプロトコル層の理論だけでなく、一般ユーザーの体験や基盤アプリケーションのロジックに本格的に浸透し始めています。
意図(Intent)中心の実行アーキテクチャであれ、クロスチェーンアグリゲーションや全チェーン対応のDEXなどの新しい形態のアプリケーションであれ、すべてが同じ目標を探求しています:ユーザーと流動性がEthereumメインネットに限定されず、頻繁にネットワークを切り替える必要もなく、統一されたインターフェースでオンチェーン資産の交換、流動性提供、戦略的操作をワンストップで完了できるようにすることです。
言い換えれば、インターオペラビリティの究極の想像空間は、ブロックチェーンをユーザーの視野から完全に切り離すことにあります——DAppやプロジェクト側が再びユーザー中心のプロダクトパラダイムに戻り、簡単に始められ、Web2に近い体験の低ハードルな環境を作り、Web3世界への新規ユーザーの参入障壁を取り除くことです。
結局のところ、プロダクト視点から見ると、主流化の鍵は全員がブロックチェーンを理解することではなく、理解しなくても使えるようにすることです。Web3が数十億人にリーチするには、インターオペラビリティこそが「最後の1マイル」のインフラなのです。
8月29日、Ethereum Foundationは「Protocol Update 003 — Improve UX」を発表しました。この文章は、EFが今年開発チームを再編した後の三大戦略方向——Scale L1(メインネット拡張)、Scale Blobs(データ拡張)、Improve UX(ユーザー体験の改善)を引き継いでいます。
その中で、「Improve UX」のコアテーマはまさにインターオペラビリティです。
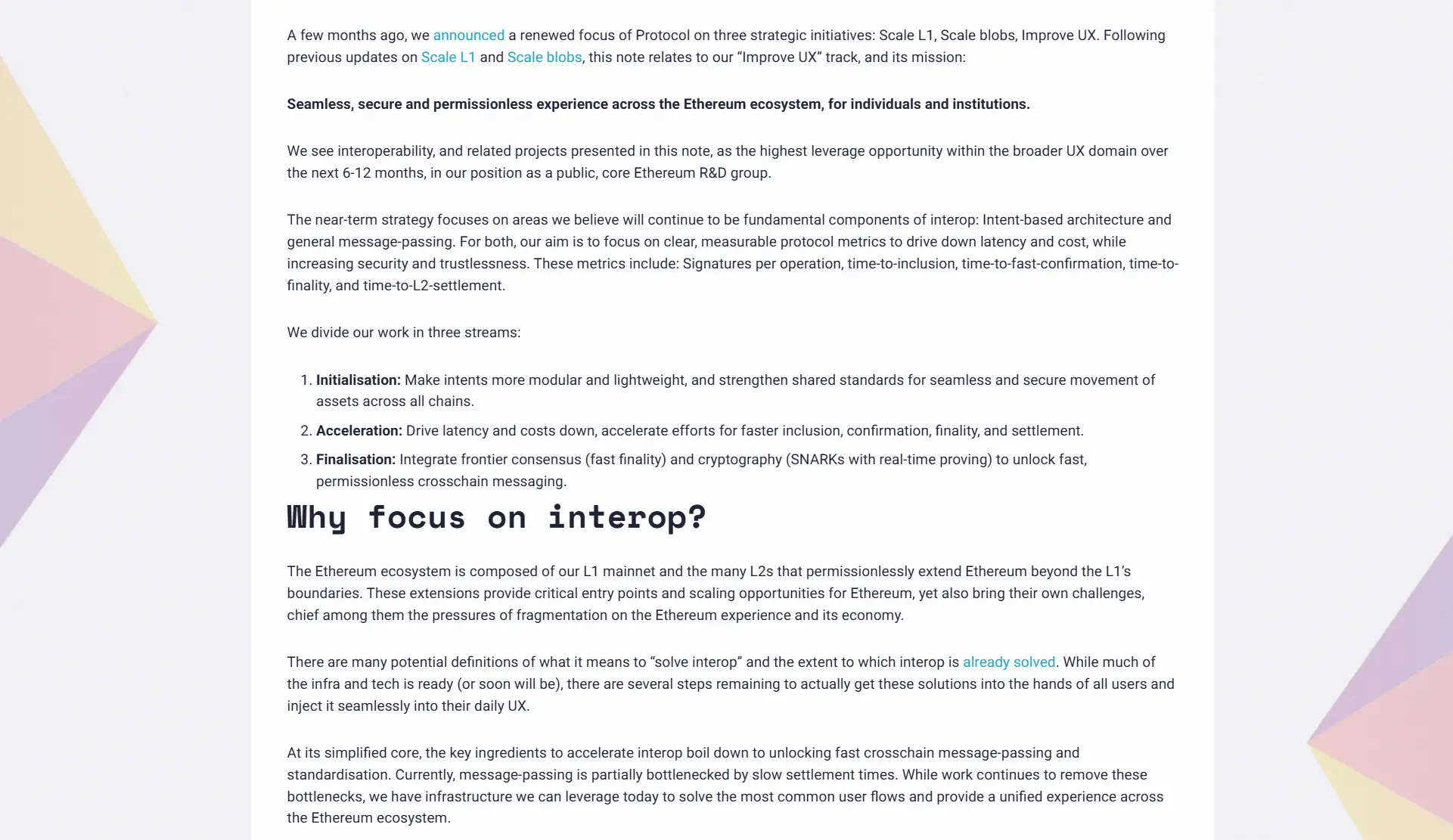
出典:Ethereum Foundation
二、「クロスチェーン」から「インターオペラビリティ」へ:EFが発するシグナル
EFのこの記事は、インターオペラビリティ(interop)をコアとし、シームレスで安全かつパーミッションレスなEthereumエコシステム体験を目指すことを強調しています。主旨は一言でまとめると、資産のクロスチェーンは第一歩に過ぎず、データ、状態、サービスのクロスチェーン協働こそが本当の「インターオペラビリティ」であり、将来的にEthereumはすべてのRollupとL2が「一つのチェーンのように見える」ことを目指しています。
もちろんEFも認めていますが、大部分のインフラや技術はすでに成熟している(または間もなく成熟する)ものの、これらのソリューションを本当にユーザーの手に届け、ウォレットやDAppの日常体験に自然に溶け込ませるには、いくつかの重要なエンジニアリングの実装ステップが必要です。
そのため、EFは「Improve UX / Interop」の開発作業を三つの並行する主軸に分割しました:初期化(Initialisation)、加速(Acceleration)、最終確定(Finalisation)。
まず「初期化」ステップは、インターオペラビリティの出発点となり、Ethereumのクロスチェーン行動をより軽量かつ標準化することを目指します。
コア作業には、意図(Intent)をより軽量かつモジュール化し、共通標準を確立し、クロスチェーン資産とクロスチェーン操作のパスを開き、異なる実行層に交換可能かつ組み合わせ可能な共通インターフェースを提供することが含まれます。
具体的なプロジェクトは以下の通りです:
- Open Intents Framework(OIF):EFがAcross、Arbitrum、Hyperlane、LI.FI、OpenZeppelinなどと共同で構築するモジュラー型意図スタック。異なる信頼モデルとセキュリティ仮定の自由な組み合わせをサポート;
- Ethereum Interoperability Layer(EIL):ERC-4337チーム主導で、パーミッションレスかつ検閲耐性のあるクロスL2トランザクション伝送層を構築し、マルチチェーン取引を単一チェーンのように自然に実現;
- 新しい標準群(ERCシリーズ):インターオペラブルアドレス(ERC-7828/7930)、資産統合(ERC-7811)、マルチコール(ERC-5792)、意図および汎用メッセージインターフェース(ERC-7683/7786)をカバー;
目標は非常に明確で、「ユーザーが何をしたいか」(宣言型)と「システムがどのように実行するか」(手続き型)を切り離し、ウォレット、ブリッジ、検証バックエンドが統一されたセマンティクスの下で協働できるようにすることです。
次に「加速(Acceleration)」段階では、遅延とコストを削減し、マルチチェーンをよりリアルタイムにします。
具体的には、「署名回数、取り込み時間、迅速な確認、ファイナリティ、L2決済」などの測定可能な指標で時間とコストを削減します。ここでの取り組みには、L1の迅速な確認ルール(強い確認を15–30秒レベルに前倒し)、L1スロット時間の短縮(12秒から6秒への研究とエンジニアリングの準備)、L2決済/出金ウィンドウの短縮(オプティミスティックの7日間から1–2日へ、またはZK証明と2-of-3の迅速決済メカニズムの導入)が含まれます。これらの施策は本質的にクロスドメインメッセージ伝達と統一体験の基礎を築くものです。
最終的には「最終確定」ステップで、リアルタイムSNARK証明とより高速なL1ファイナリティを組み合わせ、秒単位の終局を持つインターオペラビリティの形態を探求します。長期的には、これがクロスドメイン発行、ブリッジプリミティブ、クロスチェーンプログラマビリティの地図を再描画することになります。
客観的に言えば、Ethereumの文脈において、Interop(インターオペラビリティ)はもはや「資産ブリッジ」だけに限定される概念ではなく、システムレベルの能力全体を指します:
- クロスチェーンデータ通信 ——異なるL2が状態や検証結果を共有できる;
- クロスチェーンロジック実行——あるコントラクトが別のL2のロジックを呼び出せる;
- クロスチェーンユーザー体験——ユーザーは一つのウォレット、一つの取引しか見ず、複数チェーンを意識しない;
- クロスチェーンセキュリティとコンセンサス——証明システムを通じて異なるL2間で同等のセキュリティ境界を維持;
この観点から見ると、Interopは将来のEthereumエコシステムプロトコル間の共通言語と理解できます。その意義は価値の伝送だけでなく、ロジックの共有にもあります。
三、Ethereumはどのように「インターオペラビリティ」への道を開くのか?
注目すべきは、最近VitalikもEthereum MagiciansフォーラムでStage-1(第一段階)オプティミスティックロールアップの出金時間短縮に関する議論を開始し、出金期間を従来の7日から1–2日に短縮し、安全性がコントロールできる前提で、より高速な決済と確認メカニズムを段階的に導入することを提案しています。
この議論は表面的にはRollupの出金体験に関するものですが、実際には「インターオペラビリティ」三大方向の一つ——加速(Acceleration)への直接的な呼応です。
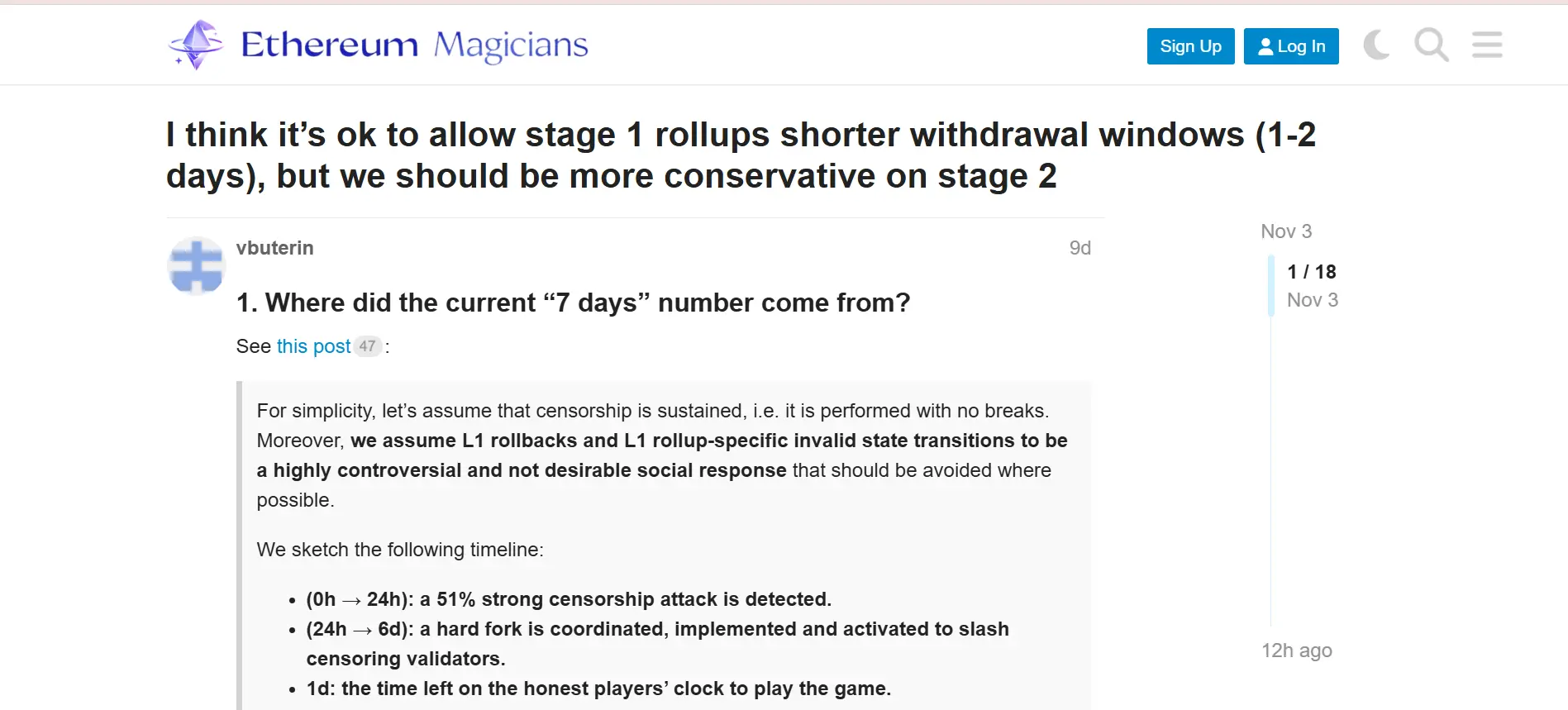
出典:Ethereum Magicians
結局のところ、出金遅延は単なるユーザーが長く待つ体験の問題ではなく、マルチチェーン協働システム全体の流動性ボトルネックです:
- ユーザーにとっては、異なるRollup間で資金が移動する速度を決定します;
- 意図プロトコルやブリッジネットワークにとっては、ソリューションの資本効率に影響します;
- Ethereumメインネットにとっては、エコシステムがより高頻度のインタラクションで一貫性とセキュリティを維持できるかどうかを決定します;
そしてVitalikの見解は本質的にこのための扉を開くものです。簡単に言えば、出金時間の短縮は、Rollupのユーザー体験の改善だけでなく、クロスドメインメッセージ、流動性、状態の迅速な流転を実現するインフラのアップグレードでもあり、この方向性はEFの「Acceleration」主軸の目標とも完全に一致しています。つまり、確認時間の短縮、決済速度の向上、移動中資金コストの削減、最終的にクロスチェーン通信をリアルタイムで信頼でき、組み合わせ可能なものにすることです。
この一連の取り組みは、11月17日(UTC+8)にアルゼンチンで開催されるDevconnectイベントとも呼応します。公式アジェンダによると、Interopは今年のDevconnectの重点テーマの一つであり、EFチームも会議でEIL(Ethereum Interoperability Layer)に関する詳細をさらに発表する予定です。
全体的に見て、これらすべてが同じ方向を指しています——Ethereumは「拡張」から「統合」への転換を完了しつつあります。
もちろん、本稿はInteropシリーズの第一弾として、インターオペラビリティこそがクロスチェーンストーリーの終局であるという基本的な問題を投げかけ、現時点でのEFの技術ロードマップからVitalikのリアルタイムな議論、標準化されたエンジニアリングの配置から徐々に短縮される決済サイクルまで、私たちが目撃しているEthereumエコシステムのもう一つの構造的アップグレードを初歩的に垣間見ました。
今後もさまざまな角度から、なぜインターオペラビリティが単なるブリッジではなく、Ethereumの未来をつなぐ基盤プロトコルであるのかを理解し続けます。
ご期待ください。
おすすめ記事:
18年のシナリオを書き換え、米政府のシャットダウン終了=Bitcoin価格が急騰?
1.1billionsドルのステーブルコインが消滅、DeFi連鎖爆発の背後にある真実は?
MMTショートスクイーズ事件の振り返り:巧妙に設計された資金集めゲーム
免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。
こちらもいかがですか?
デスクロスがBitcoinに発生、しかし強気派は底打ちの可能性を指摘
世界の暗号資産市場の時価総額は約3.25兆ドルまで下落し、恐怖感が高まっています。bitcoinはデスクロスを形成しましたが、主要なサポート付近にとどまっています。レジスタンスは96,764ドルから99,644ドルの間にあり、まだブレイクアウトは発生していません。

世界的なステーブルコイン規制の新時代:リスク管理と金融安定が焦点に

ハーバード大学、bitcoin ETFの保有量を3倍に増加—現在はMicrosoftを上回る規模に

暗号資産:恐怖指数が10まで低下、しかしアナリストは反転を予測

