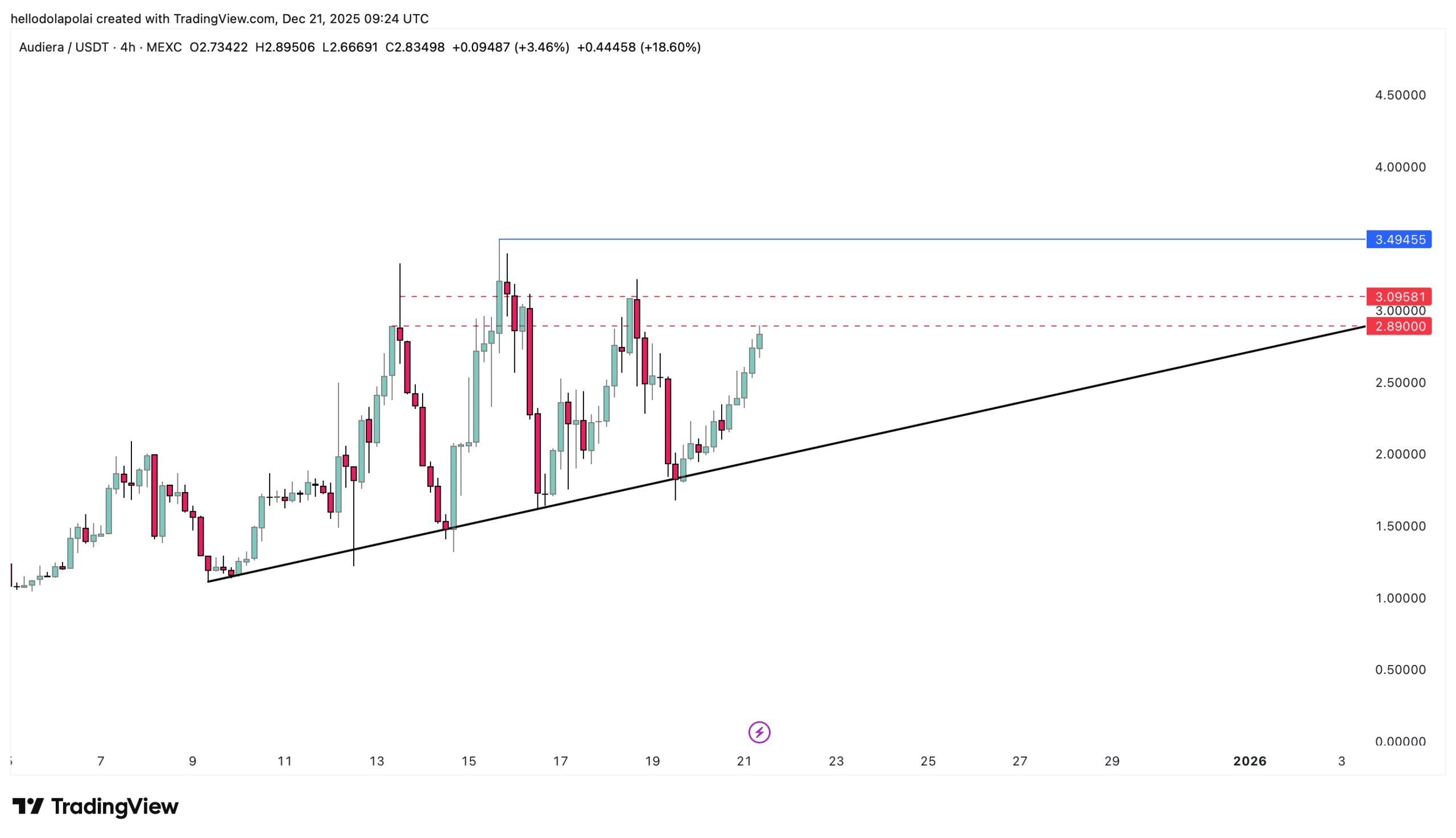主なポイント:
Bitcoinは、債務やインフレ懸念による利回り上昇時に好調だが、中央銀行が積極的に金融引き締めを行うと苦戦する。
現在の債券市場のストレスはインフレと債務主導であり、BTCはゴールドの記録的な上昇に続き、より高いベータのリターンを得る可能性がある。
米国、ヨーロッパ、日本、英国の長期国債利回りは、中央銀行が政策金利を引き下げているにもかかわらず急騰している。
米国30年国債は再び5%近くに戻り、フランスの長期国債は2011年以来初めて4%を超え、英国のギルトは27年ぶりの高値を試している。日本の30年債利回りも過去最高水準に達し、アナリストはこれを「グローバルG7債券市場の崩壊」と呼んでいる。
しかし、この懸念されるマクロ経済見通しの中で、Bitcoinはどうなるのだろうか?詳しく見ていこう。
過去の利回り急騰時におけるBitcoinの反応
歴史が示すのは、政府債券利回りの上昇に対するBitcoinの反応は、なぜ利回りが上昇しているかによって異なるということだ。時には「デジタルゴールド」として上昇し、時にはリスク資産のように苦戦する。
2013年のテーパリング・タントラムを例に挙げよう。
米連邦準備制度理事会(FRB)が量的緩和の縮小を示唆した際、米国10年債利回りは3%に急騰した。投資家はインフレと債務に不安を感じ、Bitcoinの価格は100ドル未満から1,000ドル超へと急騰した。
2021年初頭にも同様の展開があった。
ポストCOVID回復期にインフレ期待が高まり、利回りが上昇。Bitcoinはゴールドと連動し、4月には約65,000ドルまで急騰した。
しかし、2018年は逆の結果となった。
この時はインフレや債務懸念ではなく、FRBの積極的な利上げが原因で利回りが3%を超えた。債券の実質リターンが魅力的に見え、Bitcoinは同時期に約85%下落した。
このことから、Bitcoinはインフレや財政赤字、過剰な債務供給による利回り上昇時にはヘッジ資産として上昇しやすいが、中央銀行が成長局面で金融引き締めを行うことで利回りが上昇する場合は苦戦しやすいことが分かる。
今回の債券利回り上昇はBitcoinにとって強気材料か?
Bitcoinは過去3日間で4.2%上昇し、米国および他のG7諸国の長期国債利回りの急騰と歩調を合わせている。
同時に、保有者維持率も上昇しており、より多くのトレーダーがBTCをヘッジとして保有し続けていることを示している。
背景は無視できない。米国政府の債務は7月の36.2兆ドルから9月には37.3兆ドルへ、わずか2ヶ月で1兆ドル以上増加した。
大西洋を挟んで、ヨーロッパや英国も同様の借入増加に直面している。
その結果、過去最大規模の債券入札が行われ、より高い利回りでしか消化されなくなっている。これは政府債券への需要が弱まっているサインだ。例えば英国の30年債利回りは水曜日、1998年以来の高水準に達した。
ゴールドはすでに投資家行動の変化、すなわち政府債券への信頼から実物資産へのシフトを証明している。
今週、金価格が3,500ドル超の過去最高値を記録したことは、市場が急増する債務とインフレに対して積極的にヘッジしていることを示している。
歴史的に、Bitcoinはこうした資本のローテーションからゴールドよりやや遅れて恩恵を受ける。しかし一度動き出すと、貴金属よりも速く、より大きく動き、金融・財政の過剰からの高ベータ避難先として機能する。
関連記事: Winklevoss、Nakamotoが支援するTreasuryが1,000 BTCでローンチ
「中央銀行はイールドカーブの長期側のコントロールを失いつつある」と、英国のDeFi企業Satsuma TechnologyのBitcoinストラテジスト責任者Mark Mossは指摘し、次のように付け加えた:
「近いうちにYCC(イールドカーブ・コントロール)があなたの近くの債券市場にやってくるようだ。Bitcoinをロングするのはあまりにも明白な選択だ。」
多くのアナリストは、Bitcoinが2026年までに過去最高の150,000~200,000ドルに到達すると見ている。